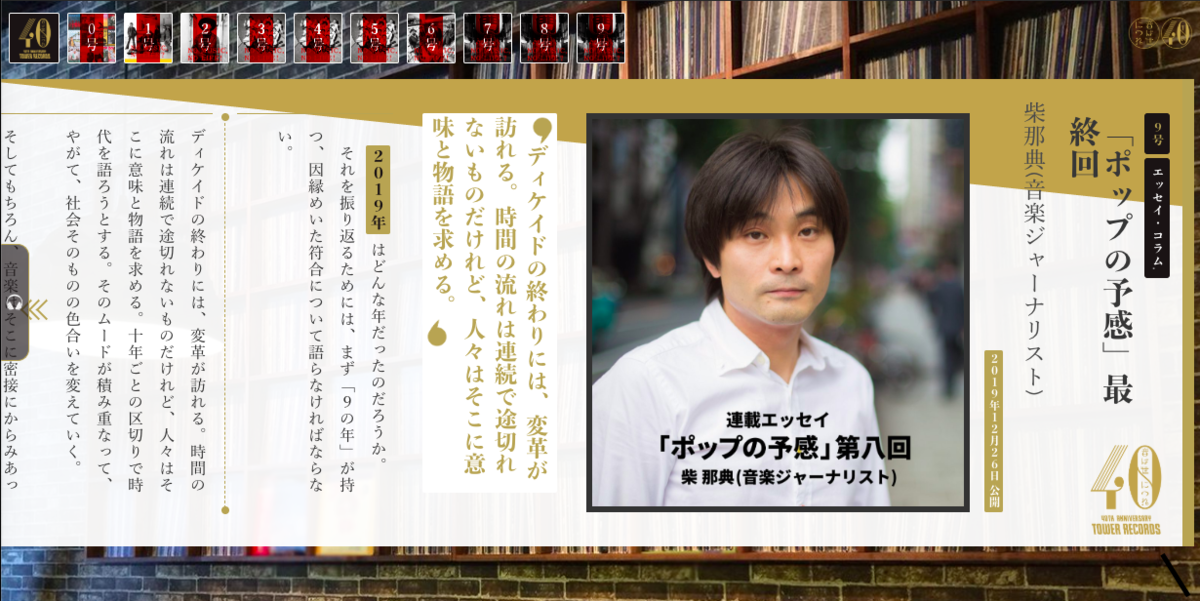
2019年はどんな年だったのだろうか。
それを振り返るためには、まず「9の年」が持つ、因縁めいた符合について語らなければならない。
ディケイドの終わりには、変革が訪れる。時間の流れは連続で途切れないものだけれど、人々はそこに意味と物語を求める。十年ごとの区切りで時代を語ろうとする。そのムードが積み重なって、やがて、社会そのものの色合いを変えていく。
そしてもちろん、音楽はそこに密接にからみあっている。
たとえば、アメリカのポルノグラフィ業界を描いた映画『ブギーナイツ』には、1979年の大晦日に行われたパーティの模様が映し出されている。「グッド・バイ70s、ハロー80s」。きらびやかで騒々しいそのムードは、時代の空気の一つの象徴だ。1979年と言えば、マイケル・ジャクソンが『オフ・ザ・ウォール』をリリースし、トレヴァー・ホーン率いるバグルズが「ラジオスターの悲劇」で一世を風靡した年。
「もう巻き戻せない。こんなにも遠くまで来てしまったのだから」。
そう歌った「ラジオスターの悲劇」では、その後の80年代に起こることが、すでに予言されていた。
たとえば、今年を代表する映画の一つであるクエンティン・タランティーノ監督の最新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』には、1969年がどんな年だったかが色鮮やかに刻み込まれている。
ウッドストック・フェスティバルからオルタモントの悲劇へ――ヒッピーたちが謳歌した60年代後半のピースフルで牧歌的な空気が大きく変質していく分岐点の一つに、映画が描いたシャロン・テート殺害事件があった。
1989年はもっとはっきりと、世界全体の枠組みが大きく変わった一年だった。北京の天安門広場で暴動が起き、ベルリンの壁が崩壊し、マルタ会談で冷戦の終結が宣言された年。ストーン・ローゼズやニルヴァーナがファーストアルバムをリリースし、フランシス・フクヤマが『歴史の終わり?』と題した論文を発表した年だ。
そんな風に、2019年も、きっと後から振り返れば沢山のことが思い出される一年になるだろう。少なくとも、人々の価値観は、目に見えて、大きく変わっている。家族や友人、仕事仲間との何気ない会話の中でも、そのことに触れることが多くあった。
そして、敏い人はもう気付いているだろう。2020年代への胎動はすでに始まっている。
たとえば、リゾがデビュー作『コズ・アイ・ラヴ・ユー』でブレイクを果たしたこと、グラミー賞で主要4部門を含む最多8部門にノミネートされるなどアーティストとして大きな成功を得たことは、「すでに2020年代が始まっている」ことの一つの象徴と言えるだろう。
「ブラック・ライヴズ・マター」も「#ME TOO」も経て、誰もがコンプレックスに縛られず、ハラスメントの対象にならず、自分に誇りを持って生きていける時代が、ひょっとしたらこの先、本当に訪れるかもしれない。彼女の醸し出すポジティヴなエネルギーには、そんな希望を感じてしまう。
ビリー・アイリッシュもが巻き起こしたセンセーションも二十年代への架け橋になるはずだ。18歳という年齢というよりも、僕は彼女の存在の重要性を「セルフ・アウェアネス」という切り口から見ている。つまり、自分自身と深く向き合うこと。
スマートフォンとソーシャルメディアの普及を経て「人々が常時接続し、相互に作用しあうこと」が当たり前になった2010年代は、メンタルヘルスが大きな問題になった時代でもあった。
様々な統計がアメリカで10代の自殺率が激増したことを示している。その要因をソーシャルメディアのせいだけにするのは早計かもしれないが、少なくとも、新しい情報技術が若者たちのメンタルに作用していることは明らかだ。XXXテンタシオン、リル・ピープ、そして先日夭折を遂げたジュース・ワールド。みな20歳か21歳で命を失った。
抗不安薬ザナックスの広まりと共に生まれた「エモ・ラップ」のムーヴメントと、そのシーンのヒーローとなるべき才能に溢れた若いラッパーたちの死は、苦悩に溢れたティーンエイジャーたちの心象の象徴でもあった。もともとダークで内向的なセンスの持ち主でもありXXXテンタシオンとも親交のあったビリー・アイリッシュが、ポップ・アイコンとして巨大なスケールの成功を経て眩しすぎるスポットライトを浴びた後に、どう歩みを進めていくか。それが次の時代の扉を開ける一つの鍵になる気がしている。
グレタ・トゥーンベリが一躍「時の人」になったのも、2019年を象徴するような現象だった。世界中の注目を浴びたきっかけは9月に行われた国連の地球温暖化サミットだったが、すでに彼女はそれ以前からアイコンになっていた。だからこそTHE1975は8月に発表した楽曲でそのスピーチをフィーチャーしたわけだし、ビリー・アイリッシュも支持を呼びかけたわけだ。気候変動にまつわる問題は、すでに危機的な状況に達している。そのことがようやくイシューとして前面化したということだ。
一方で、グレタ・トゥーンベリの言動や存在に憤慨したり嘲笑したりしている多くの人間が、いわゆる「おっさん」だったことも、とても印象的だった。その中には、トランプ大統領を筆頭に権力者の人間、企業家やエスタブリッシュメント側の人間も少なくなかった。
「toxic masculinity(有害な男らしさ)」という概念に注目が集まるようになったのも、2019年の兆候の一つだろう。強権的な態度や、暴力性や、他者を支配し屈服させることへの欲求は、これまで「男らしさ」の一つの側面として捉えられてきた。その背景には長らく続いてきた家父長制の影響もあったと思う。
けれど、その男らしさの呪縛こそが、女性を、LGBTQなどのマイノリティを、そして当の男性自身を苦しめ、生きづらくさせてきたのではないか。世界は、徐々にそのことに気付きはじめている。たとえばサム・フェンダーのデビュー作『Hypersonic Missiles』やレックス・オレンジ・カウンティの3作目『Pony』は、この「有害な男らしさ」をどう乗り越え、どう解毒していくかをテーマにした作品だ。
ポップ・ミュージックは〝予感〟に満ちている。
この連載では、ずっとそのことについて書いてきた。
日本に暮らしていると、日々、うんざりするようなニュースを目にすることが多い。気が滅入るようなことも多い。取り繕って平気な顔をしているつもりはないけれど、それでも、基本的には僕は楽観的でいようと思っている。
(初出:タワーレコード40周年サイト「音は世につれ」2019年12月26日 公開)








