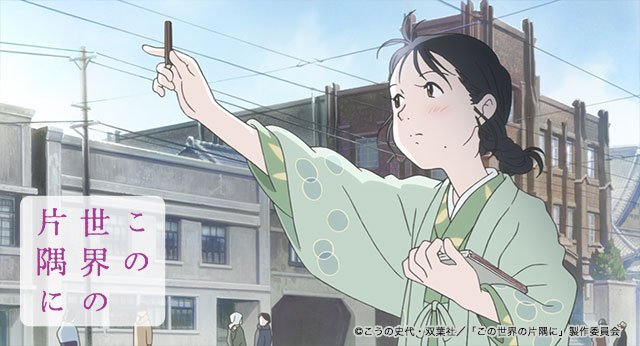古坂大魔王さん、梅田彩佳さんがMCをつとめるテレビ朝日LoGirlの番組『あやまおうのリニューアルしたよ。』にゲスト出演してきました。
というわけで。これを機会に、改めてこのブログにも書いておこう。
今年後半、文字通り世界中を席巻したピコ太郎「PPAP」の大旋風。とても面白く、興味深く、そして不思議な現象だった。きっと後から思い返しても「2016年はいろいろあったなあ」の一つの象徴として、いろんな人が鮮明に思い浮かべるんじゃないだろうか。
僕はたまたま当事者に近い場所にいるタイミングがあったので、それも含めて「一体何があったのか」を振り返っていこうと思います。
■なぜジャスティン・ビーバーに届いたのか?
まず8月25日、この動画「PPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen Official)ペンパイナッポーアッポーペン」が公開される。
これを書いてる段階で再生回数はついにほぼ1億回突破(!)。2016年のYouTubeランキングでも2位に入るというとんでもないことになっている。
多くの人が知るように、その起爆剤となったのは、公開から1ヶ月後の9月28日、ジャスティン・ビーバーが以下のツイートをしたことだ。
My favorite video on the internet 😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/oJOqMMyNvw
— Justin Bieber (@justinbieber) 2016年9月27日
これを受けてピコ太郎も以下ツイート。ここから予想外の状況が広がっていく。
じゃ…ジャスティンビーバー師匠??!!😱😱😱??! https://t.co/kG4xsMmAg3
— ピコ太郎(PIKOTARO)PPAP (@pikotaro_ppap) 2016年9月28日
でも、問題は「なぜジャスティン・ビーバーに届いたのか?」というところ。一体、どこでどうやってジャスティン・ビーバーはピコ太郎を知ったのか? 最終的には謎ではあるのだけど、僕はこんな感じで分析しています。
まず公開当日の8月25日、プロデューサーの古坂大魔王と同じ事務所で元々仲が良かったSKY-HI(AAA日高光啓)がツイッターで紹介。
ついに来た、古坂大…じゃなかったピコ太郎!
— SKY-HI(AAA日高光啓) (@SkyHidaka) 2016年8月25日
やっぱり最高、古坂大魔…じゃなかったピコ太郎!
古坂大魔王…じゃなかったピコ太郎おめでとう!
ペンパイナッポーアッポーペン/ピコ太郎 https://t.co/ceNYJCKoSB @youtubeさんから
その後MixChannelで、「まこみな」や「りかりこ」といったスター的な存在の双子JKがピコ太郎の真似を始めて、中高生の間に話題が広まっていく。
さらに、アメリカのサイト「9GAGS」がこのムーブメントを取り上げ、Facebook上でバイラルが始まる。これが9月25日のこと。
実はジャスティン・ビーバーがツイッターで紹介する前に素地は出来上がっていたわけだ。そして10月以降、PPAPはまさに世界中に「伝染」していった。イギリスのBBCでは「頭から離れない」、アメリカのCNNでも「ネットが異常事態」などと紹介。
いろんな人が真似したり、アレンジした動画をYouTubeに公開した。
さらにはSpotifyやApple Musicなどのストリーミング配信でリリースされた「PPAP」が全米ビルボード・ソング・チャートにトップ100にランクイン。同チャートのトップ100に入った「世界最短曲」としてギネス世界記録に認定された。
こないだ僕は『ヒットの崩壊』という本を出した。でも実はヒットは「崩壊」していなかった。むしろ、こんな風に予想もしていなかったところから世界的なヒットが生まれる時代になっている、というわけだ。
■「PPAP」公開の4日前に古坂大魔王がポツリと言った一言
そして。ここからは内幕的な話。
ピコ太郎が「PPAP」を投稿する4日前の8月21日、実は、僕は古坂大魔王さんと一緒にいたのです。
それはサマソニでの会場でのこと。「WOWOWぷらすと」特番の「SUMMER SONIC×WOWOWぷらすと~会場から32時間ぶっ通しニコ生SP~」で、僕はコメンテーターとして出演していた。その司会が古坂大魔王さんだった。
その日のゲストには、でんぱ組.incやA応Pやゴールデンボンバーが出演していた。前日のゲストにはRADIOFISHも出演していた。
もともと洋楽フェスとして始まったサマソニは、いまやロックもアイドルもアニソンもお笑いも何でもありの「音楽とエンターテイメントの一大絵巻」みたいな現場になっている。でも、それってすごくいいことだし面白いことだよね。そんな話を現場でした。
そうしたら、古坂大魔王さんが「実は俺も今やろうとしてることがあるんだよね」みたいなことをポツリと言った。その時は「へえ、そうなんですか」みたいにして流しちゃったけど、今思うと、あれが「PPAP」のことだったんだろうな。
ピコ太郎公式ホームページのプロフィールには「目指せ紅白歌合戦とサマソニ」と書いてあるのも、実はそのへんが背景にあるんじゃないかと思ってる。
そんなもので、あれよあれよと現象が広まっていくのを、僕は驚きと共に、そしてちょっと他人事ではない感じで見てました。そして「これは自分が誰よりも最初に音楽的に大真面目に語らねばならぬ!」と謎の使命感を持って、以下のページで解説しました。
以下自分のコメントを引用。
「約15年前から『PPAP』の原型はありました。古坂さんのルーツは80年代のテクノ。以前組んでいたお笑いコンビ・底ぬけAIR-LINEでも、1999年の『爆笑オンエアバトル』第一回チャンピオン大会で『テクノ体操』というネタを披露していました。2003年に一時お笑い活動を休止した際は、テクノグループ『NO BOTTOM!』を結成し、音楽活動に専念していたこともあります。古坂さんは1973年生まれの現在43歳。80年代後半に思春期、青春時代を送っているので、初期の電気グルーヴ、遡ってDEVOやYMOなどに影響を受けたのでしょう。そのあたりが古坂さんの音楽性の核にあり、ピコ太郎についても80年代のテクノポップの音を意識したチープな音に仕上がっているのだと思います」
「古坂さんは、mihimaruGTのプロデュースワークのほか、SCANDALが2013年にリリースしたシングル『OVER DRIVE』収録の『SCANDAL IN THE HOUSE』をプロデュースしています。この楽曲は、SCANDAL初の演奏なしの打ち込みダンスナンバーです。ほかにも、2007年にはAAAの楽曲のリミックスを手がけていて、メンバーの日高光啓とは2013年にイトーヨーカドーのCMで共演も果たしています。実は、今回ジャスティンがツイートをする前に日高がツイートしていたりもして、関係は深いはずです」
「ピコ太郎のサウンドにはEDMっぽさが一切ない。特に『PERFECT HUMAN』と比べると、一聴してそれが明らかです。『PERFECT HUMAN』はLMFAO以降のパーティーミュージックをトレースしていますが、『PPAP』は確信的に80年代のレトロなテクノサウンドを鳴らしている。リズムマシンの名機と言われるTR-808のカウベルを使っているのが象徴的。その古さがジャスティンを始めとする若い世代に刺さったんだと思います。80年代のリバイバルは00年代に起こっていて、その頃は世界的にもポストパンク、ニューウェーヴのリバイバルが流行ったんですが、その流れもすでに終わってしまった。“1周回って新しい”という時期は過ぎたけれど、2周目もまだきていない。“1.5周目”くらいなんです。そういう意味ではピコ太郎は今誰もいないポジションにいることになります。また、爆発的流行の理由に1分8秒という動画の短さもあげられます。実際に曲が鳴ってるのは大体45秒ぐらい。Twitterで動画を観る人の基本の感覚だと1分を超えるともう長く感じるので、Twitter、Instagram、Vineのタイム感にすごくフィットしているのは間違いないです」
「ピコ太郎の『PPAP』は、“ネタ”ではなく“楽曲”として10月7日に各サービスで配信がスタートしました。しかもApple MusicやSpotifyを通じての全世界配信も実現した。ということは、それらのサブスクリプションサービスを通じて世界中でこの曲が聴かれることが予想できます。そういったサービスでは聴かれた回数によってアーティストに収益が還元されるので、多額の収入が発生する可能性がある。これはお笑いと音楽の歴史を紐解くと、とても画期的なことだと思います。90年代の一発ギャグはテレビで披露して視聴者に飽きられて終わりだった。しかし、00年代に『着ボイス』が流行したことで、消費されて終わりではなく、それを収益化することが可能になった。00年代中盤に流行したムーディー勝山の『右から来たものを左へ受け流すの歌』は携帯電話向けコンテンツだけで2億円以上の売り上げになったそうです。つまり、一発ギャグが芸人にインカムをもたらすようになった。さらにピコ太郎の突発的なブレイクは、それがグローバルな規模で広がるという新しい時代の到来を意味している。これは同じように“音楽×お笑い”の芸をやっている芸人にとっては希望の持てる出来事だと思います」
この記事には古坂大魔王さん本人から「実は自分のルーツはプロディジー、ケミカル・ブラザーズ、アンダーワールドあたりの90年代エレクトロニック・ミュージック」とコメントが入ったりしたのだけど。
ちなみにその時の「SUMMER SONIC×WOWOWぷらすと」の特番にやはりゲストとして来てくれた西寺郷太さんには、『週刊現代』に掲載された書評でその時のことをこんな風に書いてくれた。
今にして思えば、ジャスティン・ビーバーがTwitterでツイートしたことから爆発的に広まった「ピコ太郎」フィーバーが、単なる「まぐれ」ではなかったこともわかる。古坂さんは「フェス(リスナー参加型音楽の魅力)」「ネットの有効活用」「そして英詞曲で、洋楽と邦楽の垣根を超える」というすべてを理解し、クリアしていたのだから。
(中略)
本書『ヒットの崩壊』で、彼が「崩壊」していると指摘する「ヒット」とは、旧態依然のメディアと作り手側が意図的に仕掛けて作る「ヒット」のこと。しかし、予想もしない角度から新たな「ヒット」は生まれうる。その主張をより鮮明に印象づけることになったのが、わずか3ヵ月と少し前の古坂さんと共演した記憶だ。出版時期から考察して9月までに執筆された本書に、夏に著者が共演まで果たした「ピコ太郎」についての記述はない。
その今年最も書くべきことが書かれなかった事実こそに僕は、まさに数週間で運命は変わるし、思いもよらぬパターンで新たなヒットが生まれる大転換時代なのだと指摘する本書の正当性を感じる。
なんか、いろいろ感慨深いものがある。
■バットを振り続ける、ということ
今年の秋から冬にかけては「なぜPPAPが世界中でヒットしたのか?」という問いに答えるお仕事がいくつかありました。
たとえば『5時に夢中』でコメントしたり。
大谷ノブ彦さんとの連載『心のベストテン』で語ったり。
柴 「とにかくやる」ってのも重要ですよね。ピコ太郎だって、今回PPAPがここまで当たったのは間違いなく偶然だと思うんですよ。
大谷 そうですよね。別に最初から世界なんて狙ってない。
柴 でも、古坂さん自身はヒットを飛ばすまで20年以上バットを振り続けてきた。
大谷 そうそう!
柴 底抜けAIR-LINE時代の1999年に爆笑オンエアバトルで「テクノ体操」というネタをやったり、NO BOTTOM!というテクノグループを結成したり、音楽とお笑いを融合した芸をずっとやり続けてきたわけで。
ヒットはたまたまかもしれないですけど、そのためには、やっぱり打席に立ち続ける、バットを振り続けるっていうのが何より大事なんだと思います。
たぶん、僕以外にも「なぜPPAPが世界中でヒットしたのか?」ということについて、沢山の人がコメントしていると思います。でも、僕としては正直、「ヒットの理由」なんて、結局のところは「後づけのこじつけ」にしか過ぎないと思うのです。
『ヒットの崩壊』なんて本を今年は書いていたから「ヒットとは何か?」みたいなことを考えることが多かったのだけれど、それって、考えてもなかなか答えがでない。当たるか当たらないかなんて、事前にはわからない。結局のところ「得体の知れない現象」にしかすぎない。だからこそ、みんなスッキリする説明を求める。もしくは「あんなもんどこがおもしろいんだ」と拒否反応を示す。
そういう「得体の知れなさ」こそがヒットの本質なのだと思います。
だから僕は、やっぱり、打席に立ち続ける、バットを振り続けるっていうのが何より大事なんだと思います。