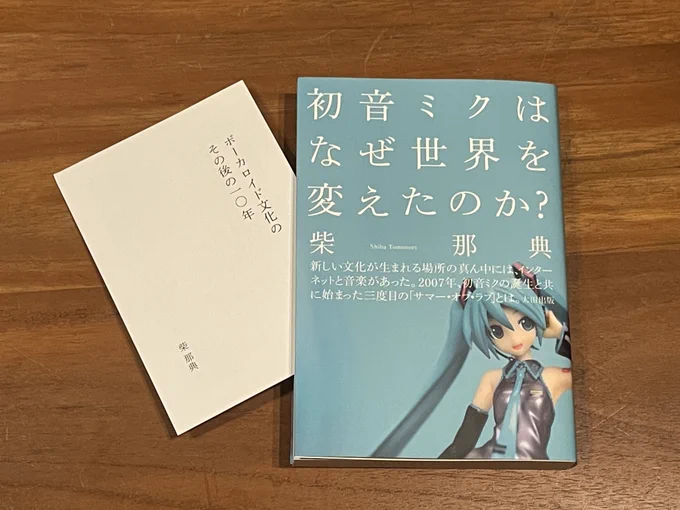例年通り、紅白歌合戦を観ながら書いています。
2023年はどんな年だったか。ここのところ恒例になっている宇野維正さんとのトークイベント「ポップカルチャー事件簿『2023年徹底総括&2024年大展望』編」でも語りましたが、やっぱりエンタテインメントの領域に大きな地殻変動のあった1年でした。そしてこれは不可逆の変化でもあると思います。
/
— LOFTch / ロフトチャンネル (@LOFTch) 2023年12月27日
アーカイブ配信&購入は1/10迄
チケット販売中!
\
宇野維正×柴那典
ポップカルチャー事件簿
「2023年徹底総括&2024年大展望」編
お笑い、映画、サマソニなどの話題から宇野さんの怪談まで今回も内容盛り沢山
《出演》
宇野維正@uno_kore
柴 那典@shiba710
🔽詳細🔽https://t.co/gn14QMv9C1 pic.twitter.com/mQB8kBzhE2
(1月10日までアーカイブ配信しているので興味ある方はぜひ)
旧ジャニーズ事務所を巡る問題や、さまざまなイシューが世を賑わせた1年でもありました。旧来の権威が解体していくさまはとてもダイナミックで、それは芸能界だけでなく政治の世界でも同時並行的に起こっていることで、そこには必然的な結びつきがあったようにも思います。
ただ、本当の変化は目に見えない社会の下部構造で起こっていることでもあると思っています。気付かないうちに、いつのまにか底が抜けていたということになるかもしれない。そんな危惧も感じています。
個人的な仕事の手応えの実感としては、ありがたいことに今年はずいぶんとメディア露出が増えた1年だったようにも思います。昨年に始まったTBSラジオの『パンサー向井の#ふらっと』という朝の帯番組へのレギュラー出演に加えて、TBSテレビ『ひるおび』でアーティストの魅力を解説するという機会もたびたびいただくようになった。
ダイノジ大谷さんとの音楽放談番組もフジテレビで放映されました。年末の特番が並ぶTVerの画面に自分の顔がサムネイルが映っているの、なんだか不思議な感じがします。
充実した仕事の場を与えてもらえていることには感謝の限り。ただ、そういう場所で活動しているせいかもしれないですが、世の中により一層「わかりやすいもの」が求められている風潮も、ひしひしと感じています。
求められていることにしっかりと応えつつも、目に見えない場所で起こっていることに耳を澄ますこと、匂いを嗅ぎ取ろうとすることを疎かにしたくはないと考えています。毎年書いているような気もするけれど、もっと思いついたことをブログに書いていこう。
というわけで、今年もありがとうございました。最後に今年の個人的なベストアルバム30枚を。2024年もよろしくお願いします。
- Noah Kahan『Stick Season (We'll All Be Here Forever)』
- boygenius『the record』
- スピッツ『ひみつスタジオ』
- Olivia Rodligo『GUTS』
- King Gnu『THE GREATEST UNKNOWN』
- The Rolling Stones『Hackney Diamonds』
- ヨルシカ『幻燈』
- Vaundy『replica』
- GEZAN with Million Wish Collective『あのち』
- 君島大空『映帶する煙』
- PinkPantheress『Heaven Knows』
- くるり『感覚は道標』
- Zack Brian『Zack Brian』
- Yuele『Softscars』
- Melanie Martinez『Portals』
- Amaarae『Fountain Baby』
- Troy Sivan『Something To Give Each Other』
- Mitski『The Land Is Inhospitable and So Are We』
- Underscores『Wallsocket』
- People In The Box『Camera Obscura』
- Ninho『NI』
- Tainy『DATA』
- マカロニえんぴつ『大人の涙』
- d4vd『Petals to Thorns』
- ROTH BART BARON『8』
- GRAPEVINE『Almost There』
- Gorillaz『Cracker Island』
- なとり『劇場』
- Cornelius『夢中夢』
- syudou『露骨』